我が家には沢山の木が植えてあるのですが、その中でも成長が早いのが月桂樹とクヌギ。引っ越してきたときに植えたので7年近くになるのですが既に2階の屋根に届く勢いです。
月桂樹はローリエとして葉っぱが利用出来るので1本植えてあると非常に重宝します。ただし成長がかなり早くそれなりに場所を取ってしまうので植える場所には注意が必要です。我が家の場合は北側の土が痩せていて他の木が育ちにくい場所に植えているのですが、そんな過酷な条件でもグングン成長するので剪定が間に合わないほどです。
クヌギの方はそれなりに陽当たりの良い場所に植えてあるのですがこちらはさらにその上をいく成長速度。一年生の苗木を植えて3~4年前に一度株元で切り、三本の株立ちに仕立てました。その株立ちになった木もかなり大きくなりこれ以上大きくなると一人で切るのは難しくなるのでそのうちの一本を再び株元で切り戻す事にしました。こうする事で株元から再びひこばえが生えてきて再生するのです。
昔から日本の里山では、この株立ちにする事で木を利用してきました。数年毎に順番に切ることで新しく苗木を植えるよりも環境負荷が少なく、安定して資源を利用出来るのです。
電気や化石燃料のなかった時代、木材は非常に重要なエネルギー資源でした。世界の多くの文明が木材を使い過ぎた事が原因の一つとなって滅んでいますが、江戸時代の場合は、幕府が森林保護を行いこの危機を回避したという歴史もあります。
そんな国だからこそこの株立ちの技術が発展したのだと思います。
 一本切った本株立ちのクヌギ
一本切った本株立ちのクヌギ
この株立ち、一本立ちの木よりも幹が細く複数本あるためしなやかで見栄えが良く、成長も穏やかになるので管理もしやすいという事で近年庭木として人気があります。一般的に売られているのは細い苗木を複数本まとめた寄せ株立ちが多く、一本立ちの木を株元で切ってひこばえから株立ちにした本株立ちは少ないです。
株立ちの苗木はそれなりに値段がするので沢山植えたい場合は懐との相談になりますが、一本立ちの一年生の苗木であれば比較的安く、自分でも簡単に植える事が出来るのでそこから株立ちに仕立てるのも面白いと思います。もちろん全ての樹種で株立ちが出来る訳ではありませんが・・・。
 椎茸の駒菌を打ち込んでいる所
椎茸の駒菌を打ち込んでいる所
今回切ったクヌギですが、それなりの太さになっていたので椎茸の原木栽培に使う事に。椎茸の原木栽培は作業的には特に難しい事はなく、用意した原木にドリルで穴を開けて駒菌を打ち込むだけです。
打ち込まれた糸状菌の一種である椎茸菌は原木を餌に増殖していき、ある程度増殖したところで繁殖の為に子実体(きのこ)を発生させるのです。今回使った”にく丸”という品種は、だいたい二夏を過ぎた頃からきのこが出来る品種ですが品種によっては一夏を過ぎた頃から発生するものもあるようです。
どのような菌においてもそうですが、温度と水分管理が大事になってきます。それともう一つ大事なのが他の菌の侵入を抑える事です。椎茸栽培においては他の菌が増殖しにくい寒い時期に菌打ちを行う事で先に菌を活着させるのです。
この辺りの菌の扱いは味噌や日本酒、納豆などの発酵食品とも共通してくる所です。味噌や日本酒が冬場に仕込まれるのはこういった事情があるのです。もちろん農閑期が重なるというのも理由の一つです。
二夏過ぎるのはまだまだ先ですがうまく菌がまわって椎茸が出来ることを願っています。




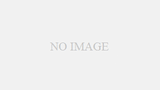
コメント