 畑に生えたきのこ
畑に生えたきのこ
春は一番忙しい時期でとにかくやることが多い。蜂は分蜂するし、畑は秋冬から春夏に切り替わり、種蒔き、畝の整備、草刈り、間引き、収穫・・・。気候が良いので作業はしやすいのですが仕事量が多すぎてなかなか思うように進みません。
それはさておき、我が家の畑ではよく”きのこ”が生えます。きのこといえば”木の子”が語源と言われるように倒木や落ち葉から生えてくるのが普通です。
一般的な畑ではまず生えてくる事はないきのこが何故生えてくるのでしょうか?
もともと糸状菌であるきのこは他の微生物が分解できない木や落ち葉などの堅くて大きな有機物を分解するという役割を担っています。もしきのこ(糸状菌)がいなければ山は落ち葉と倒木でそれこそ山積みになってしまいます。
きのこと言えば食材としてのイメージが強くて分解者としての役割はあまり知られる事はありませんが自然界では土の中にいる分解者として大切な存在なのです。
では何故畑にきのこが生えるのか?これが無肥料でも野菜が育つ大きな理由なのです。
自然農では基本的に肥料を投入することはありません。自然農では刈った草や野菜の残渣をそのまま土に還します。これらを分解するときに糸状菌(きのこ)が必要になるわけです。
糸状菌が大きな有機物を小さくしさらに他の微生物が無機物まで分解していきます。野菜はこの無機物の形ではじめて吸収出来るようになります。
自然農の畑で重要になってくるのはこの分解もさることながらアーバスキュラー菌根菌と呼ばれる糸状菌の一群の働きです。植物と共生するこれらの糸状菌は植物からエネルギー源(主にブドウ糖)をもらう代わりに植物に土壌中のリン酸を集め植物に供給するのです。これによって外からの肥料を投入しなくても植物が育つのです。
この他にも空気中の窒素を固定する根粒菌など様々な菌達の働きによって植物は育ちます。
一般的な野菜栽培のように肥料を投入すると植物は糸状菌との共生が必要なくなり畑には糸状菌が少なくなります。逆に肥料を投入しなければ糸状菌が活発に働く事になります。もちろんこれには糸状菌の餌となる有機物が必要になって来ます。この餌が自然農の畑では刈った草や野菜の残渣になるわけです。
また土中ではこの菌糸がネットワークを形成しており様々な情報のやりとりを行われている事が知られています。ただ、このあたりの事はほとんど解明されていないなので詳しくはわかりませんが。
それはさておき、きのこが生えてくるというのは糸状菌が活発に働いている証拠なので畑にとっては良い兆候だと思います。
植生だけでなく微生物を含めた全ての生物相が豊かになる、それが自然農の醍醐味ではないでしょうか。




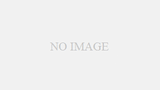
コメント